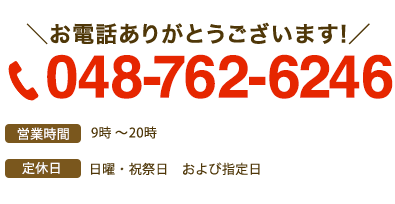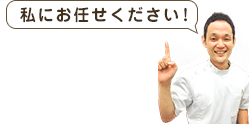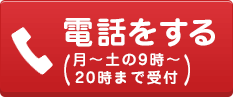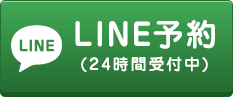はじめに
「腱鞘炎(けんしょうえん)」という言葉を耳にすると、多くの方は「指や手首の使いすぎによる炎症」と考えるでしょう。
確かにこれは正解なのですが、実際にはもっと複雑な背景があります。
同じように手を酷使している人でも「腱鞘炎になる人」と「ならない人」がいるのはなぜか?
実はそこに 筋肉のバランス と 神経の働き(相反神経支配) が深く関わっています。
今回は整体的な視点から、腱鞘炎の根本原因について詳しく解説していきます。
腱鞘炎とは?
腱鞘炎とは、筋肉と骨をつなぐ腱が「腱鞘」というトンネルを通る際に摩擦を受け、炎症が起きる状態です。
-
スマホやパソコン作業
-
育児での抱っこや家事
-
楽器演奏やスポーツ
などで繰り返し手を使うことで、腱と腱鞘がこすれて炎症が起こり、
✅ 手首や指が痛む
✅ 動かすと「カクッ」と引っかかる
✅ 朝起きると指が動かしにくい
といった症状が出てきます。
さらに進行すると「ばね指(弾発指)」になり、指の曲げ伸ばしがスムーズにできなくなることもあります。
腱鞘炎になりやすい人・なりにくい人
同じ環境・同じ動作をしているのに、腱鞘炎になる人とならない人がいます。
その差を生むのが――
-
姿勢や骨格の歪み
-
筋肉バランスの偏り
-
神経の働き方の乱れ
です。
つまり、腱鞘炎は「手首の局所的な炎症」ではなく「全身的な使い方の問題」でもあるのです。
さぼり筋と過労筋:腱鞘炎を悪化させる隠れた要因
整体の現場で腱鞘炎の方を見ていると、多くに共通するのが「筋肉の役割分担の乱れ」です。
さぼり筋とは?
本来働くべきなのにうまく使われていない筋肉。
-
例:前腕の深層筋、橈側手根屈筋
本来は手首や指を安定させる役割があるが、弱っているとサポート不足になる。
過労筋とは?
さぼり筋が働かない分、過剰に負担を背負う筋肉。
-
例:長母指伸筋、長母指外転筋、手首の伸筋群
オーバーワークで疲労・炎症を起こしやすい。
つまり、腱鞘炎は「働かない筋肉(さぼり筋)」と「働きすぎる筋肉(過労筋)」のアンバランスから生まれているのです。
相反神経支配の乱れ
筋肉は「相反神経支配」という仕組みで効率よく動きます。
例:
-
手首を伸ばす → 伸筋群が収縮し、屈筋群は自然に弛緩
-
手首を曲げる → 屈筋群が働き、伸筋群は休む
ところが、さぼり筋が機能しないと、このリズムが崩れてしまいます。
-
過労筋が常に緊張状態
-
拮抗筋がうまく弛緩できない
-
腱に過剰な摩擦がかかる
この「拮抗筋の協調性の乱れ」が、腱鞘炎が慢性化する大きな理由のひとつです。
姿勢と腱鞘炎の関係
腱鞘炎の患者さんを整体でチェックすると、多くに「猫背」「巻き肩」「骨盤の歪み」が見られます。
姿勢が崩れると――
-
前傾姿勢 → 前腕・手首に負担集中
-
肩甲骨が動かない → 支え筋(さぼり筋)が働きにくくなる
-
体液循環の悪化 → 炎症が治りにくい
つまり「腱鞘炎=手首の病気」ではなく「姿勢の病気」ともいえるのです。
整体的なアプローチ
整体では、炎症部分を直接押すのではなく、
-
さぼり筋を目覚めさせる(前腕深層筋・肩甲骨周囲筋を活性化)
-
過労筋の緊張を緩める(マッサージ・ストレッチ・温熱)
-
相反神経支配を整える(拮抗筋の協調性を回復)
-
姿勢・骨格の調整(骨盤・背骨を正し、全身のバランス改善)
-
日常生活のアドバイス(デスクワーク・スマホ・育児での使い方)
という流れで根本改善を目指します。
まとめ
腱鞘炎は「手首の使いすぎ」だけで起こるものではなく、
-
さぼり筋と過労筋のアンバランス
-
相反神経支配の乱れ
-
姿勢や体液循環の問題
といった 全身的な要因 が深く関わっています。
整体的なアプローチで筋肉の役割分担を整え、姿勢を改善すれば、痛みの改善だけでなく再発予防も可能です。
さいたま市浦和で腱鞘炎にお悩みの方へ
ななつほし整体院では、腱鞘炎を「筋肉と姿勢の問題」として捉え、根本改善をサポートしています。
「もう長引く痛みに悩みたくない」という方は、ぜひご相談ください。